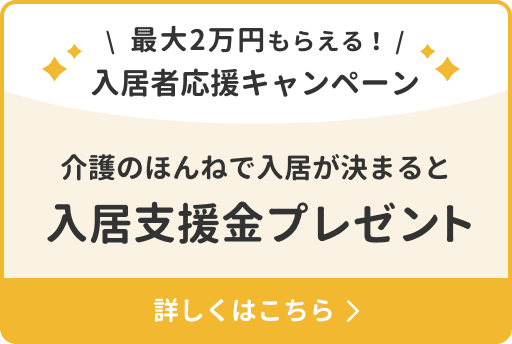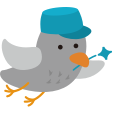介護について話し合うということ
みなさん、こんにちは。POLE・STAR株式会社の佐久間理央です。
みなさんは介護について、親・兄弟姉妹・親戚等と話し合いをしたことはありますか?
介護が必要になったらどうするか、という事だけではなく、晩年をどうやって過ごし、最期の時を迎えるのかということも事も含めて。口にしにくい話題ではあるけれど、「介護になったらどうするのか」を話し合うことは、お互いのためにやっぱり大切なことです。
元気なうちに本人が決めておいてくれればいいのですが、そうはいかないことも、また本人の意向だけではどうにもならないことも多くあります。そこに、状況が違う家族や親族が関わってくれば、また人数が増えるほど、それぞれの思いが交錯します。
話し合うことで問題を整理できる
話す機会を持つことは、本人の希望を踏まえて、みんながお互いの意見を知ることができ、共通の認識が生まれる可能性もあります。ただしそれによって、知りたくなかった家族の一面を知ることも多々あるのですが・・・それも含めて考えておくことが、介護における様々な問題を整理し軽減することにもつながっていきます。
例えば、親は最期まで自宅で過ごしたいと話をしていても、介護する人が一人、もしくは両親だけでは、その思いを貫くことは難しいのです。近くに住んでいる誰かが介護の中心者になれば、必然とそこにほとんどの負担がいくことになります。
いたたまれない思いや怒り――それでも話をする
たまにしか来ない、関わらない子供や親戚は、親にいいことしか言わなかったり、ほかの誰かが介護に対して口出しをすれば、中心になって携わっている人は、いたたまれない思いや怒りを感じます。
話し合える環境をつくっておくことで、負担を分散できたり、介護をした・しない、親のお金を使った・使わない等々、後から出てくる問題を少しでも緩和することにもつながります。
<続く>
この寄稿文は全3回の連載です。
この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています
-
関東 [12229]
-
北海道・東北 [6920]
-
東海 [4898]
-
信越・北陸 [3311]
-
関西 [6702]
-
中国 [3568]
-
四国 [2056]
-
九州・沖縄 [7729]

この記事の寄稿者
佐久間 理央
POLE・STAR株式会社ディレクター
大正大学大学院人間研究科修士課程修了(社会福祉学)。
私立国際武道大学、社会福祉法人武蔵野療園、社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会等を経て現在POLE・STAR株式会社を設立。
主に福祉や生活に関する相談、コンサルティングを行っている。
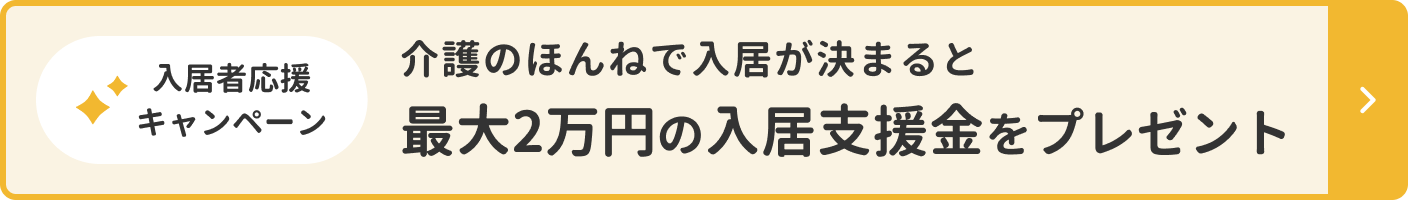
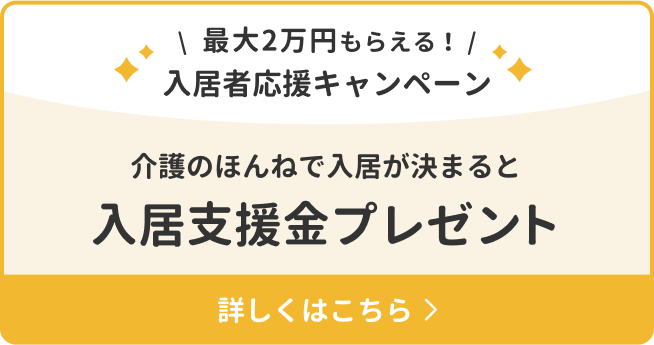
![父の介護を10年間。私のカイゴ回顧録 ~今は、“老い”を受け入れにくい時代です[前編]](https://cdn.kaigonohonne.com/images/uploads/news/article_image/1550/image?dw=600&t=1458022650)